SNSやネットメディアで「独身税」という言葉が急浮上しています。2026年度から導入予定の制度に対して、「独身者ばかりが損をするのでは?」「これは新たな差別では?」といった声も見られます。しかし、この“独身税”という言葉、実は制度の本質とはかけ離れた俗称に過ぎません。この記事では、制度の正式名称・内容・なぜ誤解が広がっているのかを丁寧に解説していきます。
関連記事
こども家庭庁が性教育人材5万人を育成──数十億円の予算は本当に“子ども”のためか?
独身税という言葉が広まった背景
SNSで「2026年から独身者に税金が課される」という投稿がバズり、メディアでも“独身税”という言葉が拡散しました。しかしこれは正式な制度名ではなく、制度に対する不満や不安を煽る目的で使われた俗称にすぎません。
正式名称は「子ども・子育て支援金制度」
制度の正式名称は「子ども・子育て支援金制度」。厚生労働省とこども家庭庁が主導し、2026年4月から健康保険料に上乗せする形で徴収が開始される予定です。
支援金は“税”ではない──社会保険料との関係
この支援金は“税金”ではなく、「社会保険料の加算項目」です。政府としては、保険料の仕組みの中で広く薄く集めることにより、安定した子育て支援の財源を確保したい考えです。
どんな人がどれくらい負担するのか?
健康保険に加入している全ての人が対象です。未婚・既婚・子どもの有無にかかわらず負担が発生します。
年収400万円の世帯で、月250〜450円程度(年約7,800円)と見積もられています。
段階的に引き上げられる予定で、2028年度には全体で1兆円超の財源を見込む計画です。
なぜ独身者に不公平だと感じるのか?
子育てをしていない人にとっては、直接的な恩恵が見えにくい
結婚できない・しない事情がある人にとっては「負担だけを押しつけられている」感覚が強い
扶養者の有無で実質的な負担の差が出る可能性もある これらの要素が合わさって、“独身税”という表現が広まりました。
制度の目的と使い道
児童手当の増額
出産・育児支援の強化(産後ケア・ベビーシッター支援など)
保育園整備や人材確保 など、支援金は「次世代への投資」として使われる予定です。
本当の問題点はどこにある?
制度設計そのものよりも、次のような論点が本質的です:
結婚・出産を自己責任とする風潮の中での「再分配」の是非
子育てを支援すべきだという全体合意の弱さ
財源確保の仕方が“誰もが納得できる構造”になっていない
単身者に対する配慮や説明が不十分 こうした問題を解決しないまま、仕組みだけを導入することでさらなる分断を招くリスクもあります。
まとめ:「独身税」という言葉に踊らされないために
「独身税」というセンセーショナルなワードが飛び交っていますが、冷静に見るとその中身は“子ども支援のための保険料加算”です。もちろん、制度のあり方には議論が必要です。しかしその議論の前に、まずは「正しい名前と目的」を知ることが、社会的対話の第一歩です。
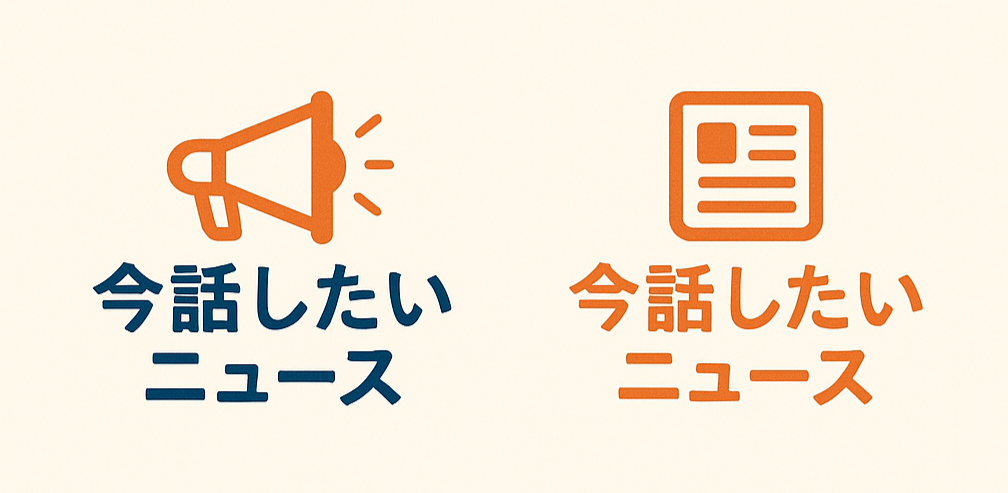
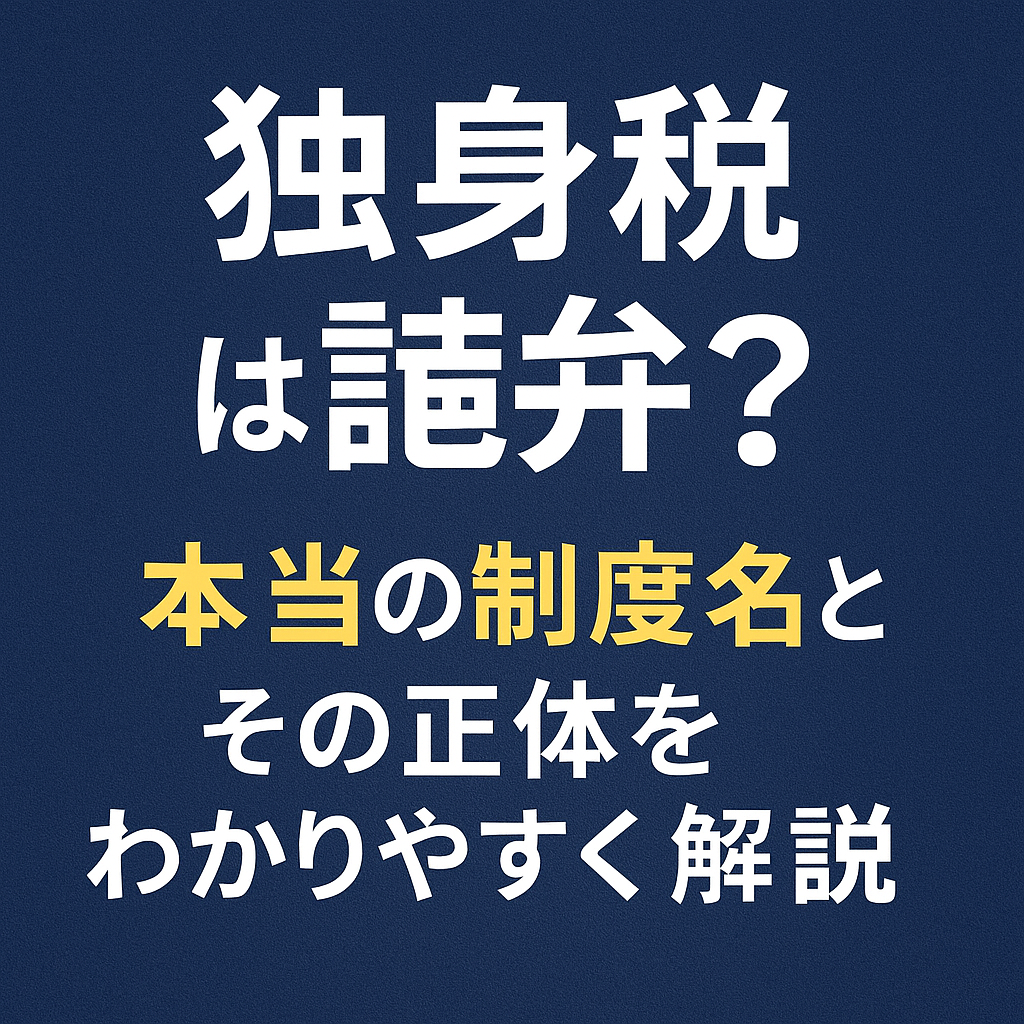
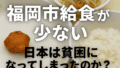
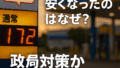
コメント